
身体の中では毎日何千個という癌細胞ができていると言われます。
DNAに障害が加えられると、DNAに記載されている情報である「遺伝子」が変容し癌化するようです。
遺伝子異常(DNA損傷)のリスクとしては、酸化、UV、栄養不足、化学物質、低酸素、ピロリ菌、肝炎ウィルスなどに起因するストレスが挙げられます。
ただ、遺伝子異常から画像診断が可能なレベルまで癌細胞が増殖するには5年から20年は経過しているようです。
また、慢性炎症や栄養不足、化学物質や生物毒素などのリスクに長時間晒されていると、脳にアミロイドβができやすくなります。ただ、アミロイドβが溜まりはじめてアルツハイマー病を発症するまでには25年ほど要すると言われます。
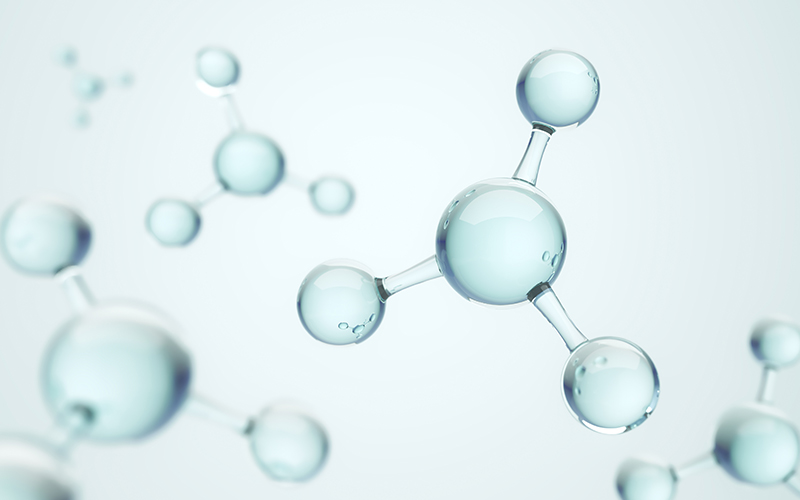
私達にはリスクに対応する仕組みが備わっており、発症までの期間が長くなっているのではないかと思われます。発症に至らず済んでいる場合も多いのではないでしょうか。
例えば、酸化ストレスの場合、呼吸などによってフリーラジカル状態の活性酸素が発生しても、SODやカタラーゼという抗酸化酵素によって、水と酸素に無害化される仕組みがあります。
また、ヒドロキシラジカルという状態になった活性酸素に自らの水素を与えて無害な水に変えるビタミンCなどの抗酸化物質も存在します。
遺伝子情報が変容してもP53などの癌抑制遺伝子が備わっており、DNAが傷ついている場所を特定し、治せる場合は修復し、治せない場合は細胞死(アポトーシス)へ誘導したり、細胞分裂を停止させたりする仕組みもあるようです。
さらに、T細胞(リンパ球の一種)が血流やリンパ系を移動して癌細胞に発現する癌抗原を体内の異物として探し出し殺傷する機能や、癌細胞をモグラたたきのように見つけては殺すというNK(ナチュラルキラー)細胞という免疫機能もあるようです。
一方、抗酸化酵素やNK細胞などの働きは、20歳頃をピークに年齢とともに効力が落ちてくるとも言われています。
そこで、リスクとなるストレスに注意しながら、免疫機能を低下させないように腸の調子を整える物質や抗酸化物質などにも配慮した食事を取るなどの生活習慣こそ、日々私達が健康の為にできることとして重要であると思われます。
(初出:ぎょうせい・月刊「税」・2025年2月号)











