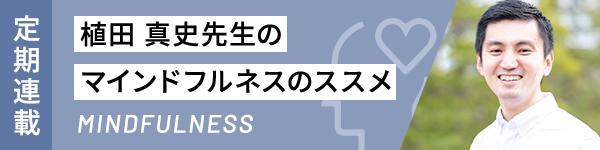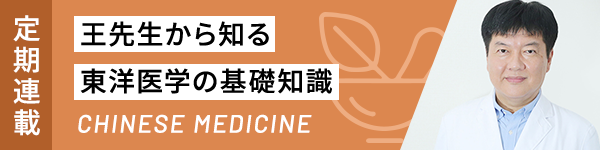私達は、花や川などの自然、茶碗などの物品、さらには人間に対しても、その「本質」を捉えようとします。分類すると名前が付けられて「本質」と「本質」の関係性が言葉で現されて、文明が生まれるようです。
エントロピーの法則

私達は生まれてから、眼や耳や鼻などで把握した感覚に、既存の文明体系に従った言葉・名前を当てはめながら覚えていきます。
山を見た、茶碗を触ったという経験には、眼や触覚という感覚器官の経験だけがあるのですが、それらを統御するものとして「私」という存在も一つの物としてこの世界に実在することが当然の前提となってきます。
しかし、茶碗は割れると、ただの破片になります。破片は砕けば粉になります。
粉も分子・原子・素粒子にまでやがて分解され、眼に見えなくなります。山ですら、日々、土は削られています。木々や草も変化しています。一瞬・一瞬変化していますが、私達はとりあえず「山」があると見做して暮らしているのです。私達の身体も、実は、約37兆個の細胞によって構成され、一瞬・一瞬細胞が死に新たな細胞が生まれるという新陳代謝が行われており、一瞬・一瞬違う物体なのです。
何らかのエネルギーが山・海・川を生み出しますが、一瞬・一瞬少しずつ崩壊しているのです。
エネルギーはまた、新たな山を隆起させるかもしれませんが、太陽の熱が増すと北極・南極の氷が解け、海に埋没するかもしれません。このようなエネルギーは恐らく地球内のものではなく、宇宙のエネルギーでしょう。
私達も、何らかのエネルギーの機縁として、人間として生命を得ます。そのエネルギーの凝縮力によって肉体の形を維持し、様々な臓器が働きます。呼吸などによってエネルギーを補いながら凝縮を保ちますが、免疫力などは、一定の年齢を過ぎると弱まっていきます。私達の身体も、免疫力などの復元力によって身体の凝縮を維持しながら一瞬一瞬崩壊しており、やがて臨界点に達すると死亡します。死亡しても肉体の塊は残るのですが、復元力はありませんので、素粒子まで分散していくのです(エントロピーの法則)。
経験的自我の変化

私達は、言葉によって「リンゴ」「バナナ」、あるいは、「井筒君」や「猿渡君」という存在を固定的に捉えますが、何らかの宇宙のエネルギーによって「リンゴ」や「井筒君」という塊に凝縮された素粒子の集まりに過ぎなくて、一瞬一瞬変容しているわけです。
言語学者である井筒俊彦は、言語によって意味づけられた「リンゴ」や「猿渡君」には、本質があり、その本質によって「非リンゴ」や「非猿渡君」と区別できると信じて皆が生きていることを示唆します。それは一つの虚構の世界なのです。「猿渡君」とはどんな人、と問われても、様々な捉え方があり、判断する人ごとの「物語」が存在します。
素粒子を山や川や人間などに凝縮するエネルギーは眼に見えません。
すると、精神、心、意識などと呼ばれるものも眼に見えないエネルギーかもしれません。私達は、一つの生物として凝縮された結果、そこに「本能」のような働きが組み込まれています。また、様々な体験をする度に、美味しかった、不味かった、好きだ、嫌いだ、などの反応経験が蓄積されて行きます。家庭や学校などでの教育でも、良いこと・悪いことが埋め込まれて行きます。
嫌いだと埋め込まれた人に出会うと自然に避けたいと思うのは、これら反応経験に照らした反射効果に過ぎないのですが、それも心の働きと捉えられます。
これらの反応経験の蓄積が「経験的自我」を構築するのです。長い間、狩猟生活を続けていた人類には、貧富の差など、恐らく無かったと思えますが、農業社会の発生以降、私達は食料などを蓄えることができるようになり、「富」という概念も発生してきたのではないか、と思われます。
このような環境の変化もあり、欲しいものは何か、良いものは何か、という反応経験も変化して、経験的自我も変わってきたのではないか、と思われます。
まとめ
経験的自我としての諸「個人」の「物語」によって構成されるのが、「世間」です。ただ、本当の「人間」とは、この「個人」ではないのではないか、経験的自我を超える「超個人」が存在するのではないか、という問題提起が、「禅」の修行を経た世界的言語学者「井筒俊彦」から提起されたのです。困難な作業ですが、私なりに紹介を試みたいと思います。
(初出:ぎょうせい月刊「税」5月号)