目次
- フリーラジカル理論
- 加齢に伴う機能低下
- まとめ

加齢プロセスの研究が進み、がん、糖尿病、脳血管疾患、運動器疾患、認知症など、高齢者に多くみられる疾患において、ライフスタイルの影響が着目されるようになっています。
フリーラジカル理論
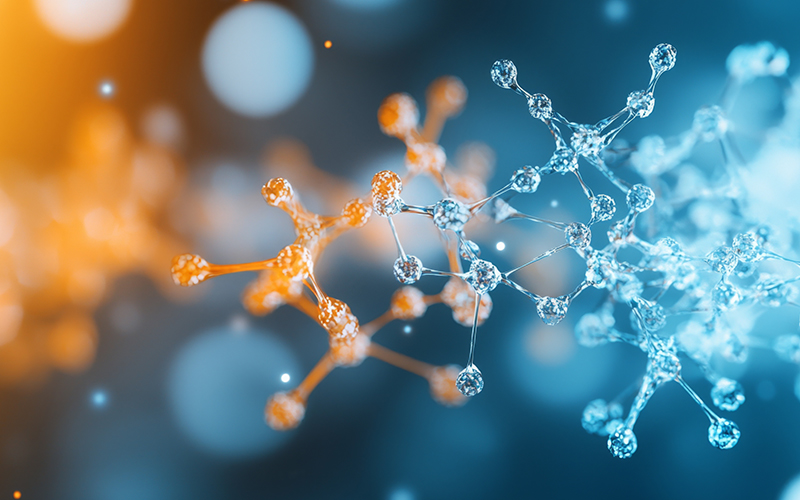
20世紀初頭には、心拍数300/分を超すマウスの寿命が約2年で、100/分~160/分の猫の寿命が約15年であるなどの事実から、体重当たりの酸素消費量の大きい動物の寿命は短いと考えられ、フリーラジカル理論へと展開します。呼吸によって取り込む酸素の一部がフリーラジカル化した活性酸素(対をなさない電子を持つ分子)となり、他の分子を攻撃し電子を奪い酸化反応の連鎖(酸化ストレス)が生じるというものです。
一方、DNAの損傷を防ぐため抗酸化システムが存在し、DNA損傷を修復できずに分裂が止まった老化細胞に対しては、アポトーシスという細胞死のプログラムが発動され、老化細胞を異物として破壊するT細胞という免疫機能もあります。このように、私達の身体には、約37兆個の細胞活動を安定して恒常的な状態に保とうとする仕組み(恒常性=ホメオスタシス)が備わっています。
加齢に伴う機能低下

しかし、酸化ストレスを抑制する抗酸化システム機能も、アポトーシスに誘導する機能も、T細胞などによる免疫機能も加齢により低下してしまうのです。ただ、これら加齢に伴う機能低下は、食事や運動、ストレスコントロールなどのライフスタイルのあり方によって、ひとり一人大きく異なる可能性が明らかにされてきています。
また、細胞分裂するごとに短くなるテロメア(染色体の末端のタグ)は、ある程度短くなると分裂できなくなるので「命の回数券」と呼ばれ、サーチュイン遺伝子は染色体を安定化させるので長寿遺伝子と呼ばれます。テロメアを延ばし、長寿遺伝子を活性化させれば健康長寿に繋がるのではと期待されますが、そのポイントもライフスタイルにあるようです。
まとめ
病気を防ぎ健康寿命を延ばすためには、日々のライフスタイルの工夫によって老化を遅らせるよう努めることが求められているのです。
(初出:ぎょうせい:月刊「税」6月号)












