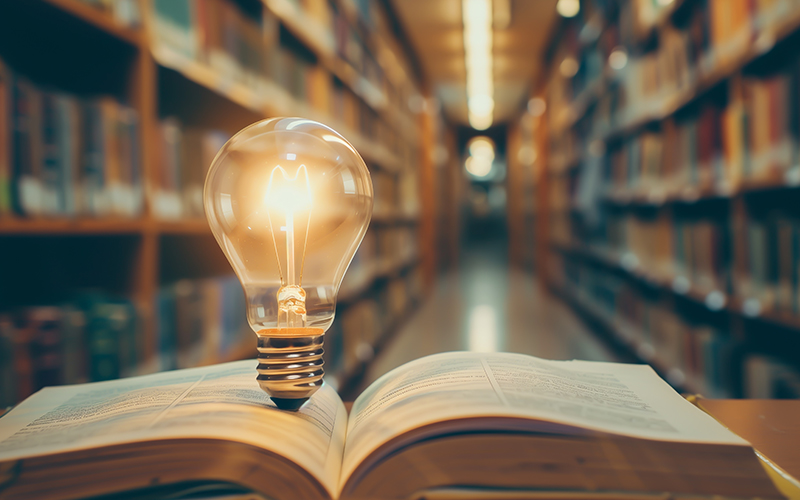
井筒俊彦は、悟りへのプロセスを説明するために「①山は山である⇒②山は山ではない⇒③山は山である」という禅の言葉を例示しています。
「①山は山である」というのは、眼で見て、手で触るといった感覚器官を通して表層意識が知覚した山が現実にイメージ通り実在していると思う常識的な反応です。
「山」という言葉により「非山」と区別される不変の本質によって固定されているという認識が前提にあります。
表層意識で認識できるもの

ところで、私達が物を見る場合、あらゆる温度を有する物体が光子を発している中で、その一部が私達の眼の網膜にぶつかって視覚のプロセスに進んでいる訳です。
また、物質は色を有していないのに、眼が把握できる波長の電磁波(光子)だけを変換して色として認識しています。
すなわち、感覚器官を通して認識する世界は本当の実在世界である「物自体」の一部なのだというカントの考え方がより現実的です。
ただ、この考え方に立っても、感覚器官を通して「山」として表層意識で認識できるものは、それだけで実在していることになります。
しかし、「山」も素粒子の一時的な集まりに過ぎず、一刻一刻変貌しており、固定された本質などないのだ、という諸行無常を理解すると、目の前の「②山(のイメージ)は山(の実在)ではない」ということになります。何らかの素粒子の集まりが網膜にキャッチされた後、多段階の生理的プロセスを経て「山」という映像イメージとして創造されているだけなのです。経験的世界(世間)のあらゆる存在者が、本来、無「本質」なのだと思い定めることが悟りへの第一歩であると井筒は指摘します。
深層意識と存在の本質

では、言葉によって輪郭が与えられる前、感覚器官によってイメージされただけの段階では、外界はどのように現れるのでしょうか?
井筒は、サルトルの小説「嘔吐」から次の引用を示します。「マロニエの根はちょうどベンチの下のところで深く大地につき刺さっていた。それが根というものだということは、もはや私の意識には全然なかった。あらゆる語(ことば)は消え失せていた。そしてそれと同時に、事物の意義も、その使い方も、またそれらの事物の表面に人間が引いた弱い目印の線も。背を丸め気味に、頭を垂れ、たった独りで私は、全く生のままのその黒々と節くれ立った、恐ろしい塊に面と向かって坐っていた。」
このように言葉が脱落し、「本質」が脱落してしまえば、どこにも境目のない「存在」そのものだけが残るのです。サルトルの表現によれば「ぶよぶよした、奇怪な、無秩序な塊りが、怖ろしい淫らな裸身」のまま怪物のように現れてくるのです。この瞬間に意識の深層が垣間見られると井筒は言います。
深層意識レベルで眺めることができれば、一切の存在者が「もの(物)」として現れる以前の根源的な存在には、名前が無い「無秩序な塊り」という段階があり、その名前の無い知覚内容を思考し、「山」や「谷」などの概念と結びつけて世界が立ち上がっていくプロセスを体験できるわけです。人間のそれぞれの個体の感覚器官が駆使されていますが、個体としての「私」も世界の一部として組み込まれるので、個体の「私」ではない「自分」がただ「眺めているという体験」だけがあります。これは、宇宙の生命エネルギーそのものが人間の感覚器官を駆使して思考を加えながら世界を創り出している体験なので「③山(のイメージ)は山(のように見える宇宙エネルギー)である」という実在が深層意識において言葉を用いずに覚知されるようです。
一方、表層意識レベルでは、このプロセスを省略して始めから「既に出来上がったもの」として私達が日常的に経験する世間が現れ、それを見ている個体としての「私」を制約する存在になっていました(①の状態)。この表層意識が捉える「世間」が言葉の無い深層意識レベルで捉える「世界」と同時に現れている状態では、「世間」は無「本質」となり(②の状態)、深層意識レベルで、いわば宇宙と一体となった「自分」は瞬間瞬間次々と「世界」を立ち上げている既成事実の無い自由な世界を体験しているはずです(③の状態)。この状態がいわゆる「悟り」と言われるものかもしれません。
まとめ
この意識の深層を覚知するため、古来、様々な修行が実践されてきました。
次回は、ルドルフ・シュタイナー「自由の哲学」なども参考にしながら、少し紹介したいと思います。
(初出:ぎょうせい:月刊「税」7月号)











