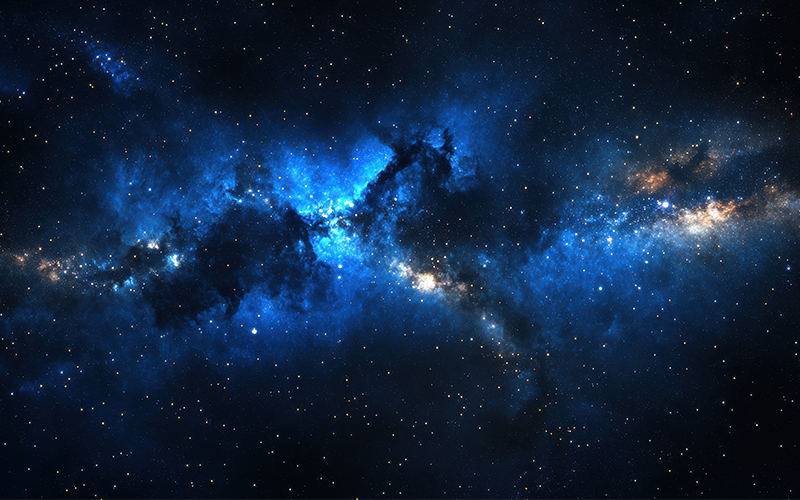
人間、地球、太陽系、天の川銀河といった目に見える物質による世界を創り出しているのは、ダークマターという目には見えない宇宙の巨大なエネルギー空間でした。私達も天の川銀河とともにダークマターの中に浮いている存在です。
ただ、私達は、物質であり、生物であり、動物であると同時に人間であることを忘れてはならないでしょう。
物質世界の創造

物質世界の創造は、正の電気を帯びた粒子である陽子と負の電気を帯びた電子が互いに電気的に引き合う力を利用して構成される原子からはじまります。最も簡単な原子である水素から星が創られ、星の内部で炭素や鉄などの原子が創られます。星の崩壊とともに様々な原子は拡散し、2つ以上の原子から様々な分子が構成され物質世界が生まれるのです。陽子と電子のバランスは私達の健康にとっても極めて重要です。このバランスが崩れることが炎症につながり、癌のような病気から日々の身体の不調に関係していると言われています。
動物・植物・細菌などの生物の基本構成単位は細胞です。細胞は、栄養を取り込みエネルギーに転換する呼吸を行い、遺伝情報と自己複製能力があります。私達の生命活動も、細胞レベルで維持されています。
自ら動いて食料を求める能力を有した生物が動物です。動物には、食欲の他、睡眠欲や性欲など本能が備わりました。私達も本能によって意識せずに日常生活を送れる訳ですが、過度な本能はエゴイズムを喚起し、人間の在り方に大きな影響を与えることになります。
人間の祖先(旧人)がチンパンジー(類人猿)と枝分かれしたのは約600万年前後だと言われますが、人間とチンパンジーのDNAの違いは2%に満たないそうです。しかし、約20万年前に誕生したホモサピエンスには決定的な違いがありました。言葉を使うことで現生人類となったのです(人間の誕生)。文字となった言葉は、山だ、川だ、海だ、というように、周囲のあらゆるものを区別し名前を付けていくことで、人間が理解する表層意識の世界を形成していきました。
一般に動物は、生命活動を維持し大自然の中で生き残るため、本能を働かせ無邪気にあれこれ悩むこともなく過ごしているものと思われます。
世界を形成していった人間は、やがて農業を始め定住して富の蓄積が可能となると、社会を形成します。他人との比較の中で自己固執も始まります。人間関係による悩みや苦悩など、不幸と呼ばれる感情を生むようになります。生命維持と矛盾する自殺すら発生するようになります。
私達は、頼んでないのに生まれてきて頼まないのに死んでいくのです。ダークマターなのか名前はとにかく、何らかのエネルギーによってある目的のために生かされているのが私達ではないでしょうか。
理性という能力

言葉を使い世界を形成したのは、理性という能力ですが、ダークマターは私達を悩ませるために理性を与えたはずはありません。また、理性は、遺伝子の生き残りに資するためのエゴイズムの支配下にあるものでもありません。
この物質世界がダークマターという目に見えない濃密なエネルギー空間から生まれるように、私達も、目に見えないイメージから、建物や様々な新たな物質世界を創造することができますし、哲学や思想など目に見えない精神世界を共有することも可能です。宇宙のエネルギーの延長線上に新たな世界を創造する目的で特別に人間に与えられた能力が理性だと考えられます。
さらに、人間には、エゴイズムさえコントロールできる力(エネルギー)があります。恐らく深層意識に直観する良心ではないでしょうか。私達が良心に従い理性を活かすことは宇宙の秩序に沿った使命なのです。
まとめ
深層意識で宇宙と直結する私達には、物質世界と精神世界を繋ぐ役割が求められているように思います。
脳や心臓などの臓器を活用して、私達の心や身体を動かしている生命エネルギーこそ、人間の本当の存在なのかもしれません。
言葉や文字の悪弊による自己固執を乗り越えた悟りを求めて、古来、人々は修行を繰り返しました。
良心を直観することで本当の自分の存在を掴もうとしたのでしょうか。
方法論と併せてもう少し考えてみたいと思います。
(初出:ぎょうせい月刊「税」9月号)












