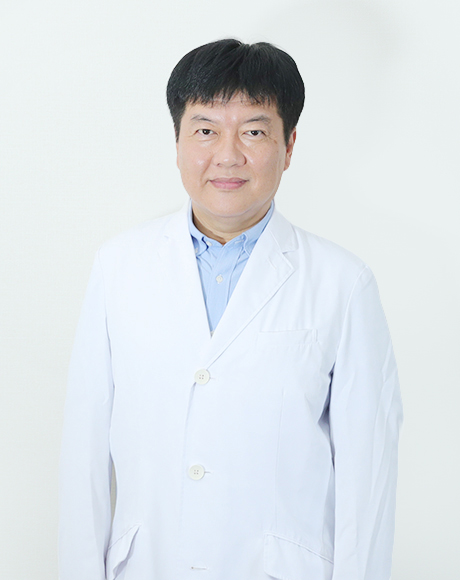中国茶の歴史
日常生活に欠かせないお茶(中国茶)は、誕生から長い歳月を経て、中医学の理論を基に茶文化として発展してきました。また、貿易の発達により世界中に広がり、定着していきました。
文化としての茶
中国では商の時代(紀元前1700~紀元前1100年頃)にはすでに、「4月に茶を摘む」という記録があり、周の時代(紀元前1066~紀元前168年)には「茶を貢ぎ物として朝廷に捧げた」という記録が残っています。
後漢の時代になると巿場で茶葉を買い、煎じてから飲む習慣が定着してきました。
また唐の時代(618~907年)には、寺では「午後は食事をとってはいけない」という規則ができたため、茶室を設置してお腹を空かせた僧侶たちのために茶を提供するようになりました。このことが信者たちにも影響を及ぼし、茶がさらに流行しました。
このような背景のもとで、陸羽(りくう)は「茶は努力・端正・節約など徳のある人に最も適切な飲み物である」と述べ、茶を飲むことは上品な行為だとされるようになりました。「茶(ちゃ)経(きょう)」によって、茶を飲む行為は「礼・仁・雅・和・静などの精神を表す」という今の茶道にも通じる、ひとつの文化としても栄えるようになったのです。

薬としての茶
茶が長い歴史を経てこれほど広まった理由は、茶がもっている多くの働きにあります。中国古代の文献には次のようなエピソ一ドがありました。
神農という人物が薬を調べるために山々を歩いて回り、さまざまな草木を試食したときに、多くの毒にあたって巨大な茶樹の下に倒れてしまいました。すると茶葉に留まっていた露が口元に垂れてきて、神農の開いた口に流れ込み、その雫(しずく)を飲んだために命が助かったそうです。
この話からもわかるように、茶は解毒薬としても利用されてきました。
後漢の時代(25~220年)の書物には、茶には「気持ちを楽しくする」「心を安らかにして気を養う」「イライラやのどの渇きを止める」「熱毒邪に侵された下痢を治す」「利尿」「痰を取り除く」「身体を軽くして若さを保つ」「長期間飲むと瘦せる」「脂肪を取り除く」「飲み過ぎ・食ベ過ぎを治す」などの効果があるという記録が残っています。
清代(1616~1912年)の『本草(ほんぞう)求(きゅう)真(しん)』(編:黄宮綉(こうきゅうしょう))にも「茶には甘味があり、寒の性質をもつ。肺に入って身体にたまっている痰飲を溶かしたり、心の熱毒を清したり、脂肪を排泄したり、宿食を解消したりする効能がある。よって、食積・頭がボーッとする・よだれが垂れる・大小便の不調・消渴・吐血・鼻血・血便・火傷などの症状に有効である」と書かれています。このように、茶は薬として長く使われていたことがわかります。

茶の普及
茶葉は南北朝時代(439~589年)に中国から東南アジア、インド、朝鮮半島、日本、ヨーロッパへ輸出され始め、次第に世界中に広がっていきました。
17世紀のイギリスではポルトガルからチャ一ルズ2世に嫁いだキャサリン王妃の美しさの秘密が紅茶にあることがわかり、上流階級から庶民まで紅茶を飲む習慣が広がりました。フランスでもはじめ紅茶は身体に有害なものとみなされていましたが、ルイ14世の頭痛が紅茶で治ったことから流行するようになりました。
今では、茶は健康に最もよい飲み物として日常的に利用されており、地域によって飲む習慣も違います。中国の広東省・福建省・雲南省・貴州省では、烏龍茶や普洱茶をよく飲み、浙江省・北京では龍井茶をよく飲みます。ジャスミン茶は緑茶と茉莉花をベースとして作られたよい香りの茶で北京ではポピュラーな茶として好まれています。
参考文献
- 関口善太著.〈イラスト図解〉東洋医学のしくみ.日本実業出版社,2003
- 辰巳洋著.実用中医薬膳学.東洋学術出版社,2008
- 平馬直樹・浅川要・辰巳洋著.オールカラー版 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書.株式会社ナツメ社,2014
- 辰巳洋著.薬膳茶のすべて.株式会社 緑書房,2017
- 仙頭正四郎著.最新 カラー図解 東洋医学 基本としくみ.株式会社西東社,2019