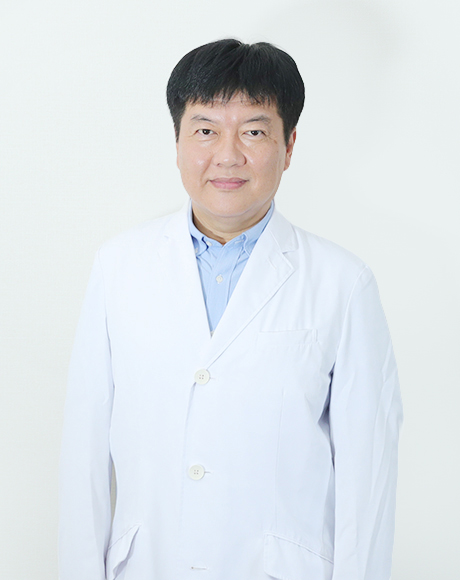目的別・薬膳茶に使う食薬 温(おん)

温性・熱性、辛味・甘味などの性味をもつ食薬で、
体表や臓腑を温め、寒邪を取り、臓腑の働きの虚弱による冷え、無気力、疲れなどを改善します。
辛温解表類(しんおんげひょうるい) 寒気を感じるときに体表を温める
風邪のひき始めに出る熱・寒気・鼻水・鼻つまり・頭痛・のどの痛み・身体の痛み・食欲不振などの症状があるときには、辛温解表類の食薬がおすすめです。
ここで紹介する食薬は性質が温性、味が辛味で発散する力が強いため、体表を温めることができます。晚秋から冬・早春の養生にも適した食薬です。
温裏類(おんりるい) 身体の奥を温める
気温・飲食・環境の要因で臓腑・血脈・骨が冷えて体調が悪くなるため、身体を温めることは重要です。このとき、身体の奥を温める温裏類の食薬を用います。この種類の食薬は香辛料が多く含まれているので、使用量に注意しましょう。
助陽類(じょようるい) 身体を強壮しながら温める
虚弱体質、加齢とともに臓腑の働きが低下し、体内の陽気が不足して、臓腑から背中や胸の冷痛・動悸・冷汗・腹痛・むくみ・四肢冷感・足腰冷痛・頻尿感・下痢・生理痛・生理不順の冷えや疼痛などの症状が現れます。これらの症状を緩和するのが助陽類の食薬で、虛弱した臓腑を温め、働きを增強し、陽気を補給します。

辛温解表類(しんおんげひょうるい)
生 姜(しょうきょう)――ショウガ科 性味 温、辛 帰経 肺・脾・胃 常用量 3~9g
期待される効能
- 解表散(げひょうさん)寒(かん)・温肺止(おんはいし)咳(がい):風寒邪気による悪寒・無汗・頭痛・身体の痛み・咳・白い痰・喘息
- 温中止嘔(おんちゅうしおう):脾胃虚寒による胃の冷え・痛み・嘔吐・食欲不振
紫蘇(しそ)――シソ科 性味 温、辛 帰経 肺・脾 常用量 3~6g
期待される効能
- 解表散(げひょうさん)寒(かん):風寒邪気による発汗・発熱・咳・痰
- 行(こう)気(き)寛中(かんちゅう):気滞による胸のつかえ・吐き気・嘔吐・つわり・胎動不安
新鲜な葉を「大葉」とよび、種の「紫蘇子」は咳・白い痰・便秘に使います。
桂 枝(けいし)――クスノキ科 性味 温、辛・甘 帰経 心・肺・膀胱 常用量 3~6g
期待される効能
- 発汗(はっかん)解(げ)肌(き):風寒湿邪気による悪寒・悪風・頭痛・発熱
- 温通(おんつう)経脈(けいみゃく):関節痛・生理痛・閉経
- 助陽化(じょようか)気(き):胸陽不振による冷え・動悸・胸と腹部の痛み・めまい・痰
桂枝は樹木の細い枝の部分を使います。肉桂は同じ樹木の樹皮を使いますが効能は異なります。
白芷(びゃくし)――ゼリ科 性味 温、辛 帰経 肺・胃・大腸 常用量 3~9g
期待される効能
- 解表散(げひょうさん)寒(かん)・祛風(きょふう)止痛(しつう):風邪・寒邪による悪寒・頭痛・身体の痛み・歯痛・鼻つまり・鼻水
- 燥湿止帯(そうしつしたい)・消腫排(しょうしゅはい)膿(のう):寒邪・湿邪によるおりもの・癰腫瘡毒(ようしゅそうどく)(皮膚・乳腺・腸の急性化膿性疾患)
香薷(こうじゅ)――シソ科 性味 微温、辛 帰経 肺・脾・胃 常用量 3~6g
期待される効能
- 発汗(はっかん)解表(げひょう):春の風邪寒邪による悪寒・発熟・無汗・頭痛
- 化湿(かしつ)和中(わちゅう)・利水消腫(りすいしょうしゅ):湿邪による胸のつかえ・嘔吐・下痢・むくみ・尿量減少
参考文献:
- 関口善太著.〈イラスト図解〉東洋医学のしくみ.日本実業出版社,2003
- 辰巳洋著.実用中医薬膳学.東洋学術出版社,2008
- 平馬直樹・浅川要・辰巳洋著.オールカラー版 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書.株式会社ナツメ社,2014
- 辰巳洋著.薬膳茶のすべて.株式会社 緑書房,2017
- 仙頭正四郎著.最新 カラー図解 東洋医学 基本としくみ.株式会社西東社,2019