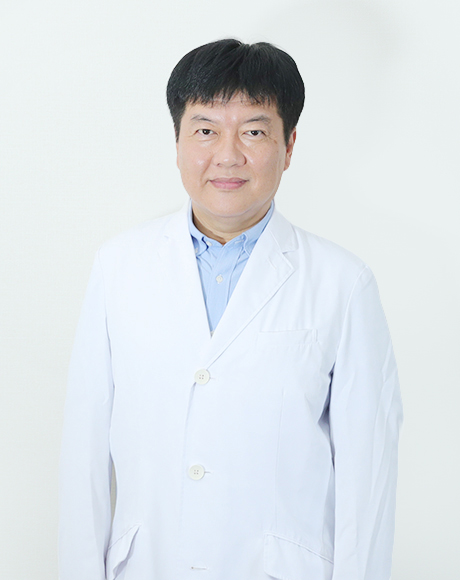涼性・寒性または平性、辛味・苦味・鹹味などの性味をもつ食薬で、体表と臟腑の異常な熱を冷まし、臟腑の陰陽失調による虚熱を取り除きます。
辛(しん)涼(りょう)解表類(げひょうるい) 体表の発熱を取る
風邪・暑邪・火邪・燥邪による身熱・くしゃみ・のどの痛みや渇きなどの体表の熱には熱を冷ますことが必要で、辛涼解表類の食薬をおすすめします。この種類の食薬の性質は涼性、味は辛味。発汗作用があり、体表の熱を取ります。春~夏・秋にもおすすめです。
清熱類(せいねつるい) 体內の異常発熱を取る
身体の内部から熱を生じることがあり、次のような症状が現れます。
肺熱による症状:発熱・咳・黄色い痰・のどの痛み・胸の痛み
心熱による症状:顔が赤い・にきび・吹き出物・口内炎・発汗・尿の色が濃い
肝熱による症状:口の苦み・目が赤い・耳の痛み・排尿痛・尿の色が濃い
胃熱による症状:食欲旺盛・口臭・のどの渇き
膀胱熱による症状:排尿痛・尿の色が濃い・血尿など
大腸熱による症状:ガスが臭い・便秘・下痢・便の悪臭
現れる症状の違いによって食薬を選択します。
滋(じ)陰類(いんるい) 身体を滋養しながら熱を取る
血・津液・精などの陰液を滋養しながら身体を潤し、肺の空咳・咯血・胸痛・微熱・寝汗・胃の痛み・のどの渴き・食欲不振、肝の微熱・いらだち・めまい・手の裹の熱感・右脇肋の痛み、腎の耳鳴り・微熱・寝汗・足腰のだるさなどの乾燥・発熱の症状を改善する食薬です。
これらの食薬は滋補により胃を傷めやすいので、砂(しゃ)仁(にん)、陳皮(ちんぴ)など行気健脾のものを適度に入れます。
辛(しん)涼(りょう)解表類(げひょうるい)
桑(そう)葉(よう)――クワ科 性味 寒、苦・甘 帰経 肺・肝 常用量3~9g
期待される効能
- 疏散風熱(そさんふうねつ):外感風熱邪気による体表の発熱・軽い咳・頭痛・のどのかゆみと痛み
- 清肺潤燥(せいはいじゅんそう):肺熱による咳・空咳・少量の痰,粘稠で黄色い痰
- 平(へい)抑(よく)肝(かん)陽(よう)・清(せい)肝(かん)明目(めいもく):肝(かん)火上炎(かじょうえん)・肝(かん)陽上亢(ようじょうこう)による目の充血・かすみ目・頭痛・めまい・怒りっぽい
牛蒡子(ごぼうし)――キク科 性味 寒、辛・苦 帰経 肺・胃 常用量3~12g
期待される効能
- 疏散風熱(そさんふうねつ)・宣肺祛(せんはいきょ)痰(たん):外感風熱邪気による発熱・目の赤み・かゆみ・咳・多量の痰
- 利咽透疹(りいんとうしん):外感風熱邪気によるのどの腫れと痛み・麻疹や風疹の透発(毒素を外へ出すこと)が不十分なとき
- 解毒消腫(げどくしょうしゅ):吹出物・皮膚や皮下の急性化膿性疾患
参考文献
- 関口善太著.〈イラスト図解〉東洋医学のしくみ.日本実業出版社,2003
- 辰巳洋著.実用中医薬膳学.東洋学術出版社,2008
- 平馬直樹・浅川要・辰巳洋著.オールカラー版 基本としくみがよくわかる東洋医学の教科書.株式会社ナツメ社,2014
- 辰巳洋著.薬膳茶のすべて.株式会社 緑書房,2017
- 仙頭正四郎著.最新 カラー図解 東洋医学 基本としくみ.株式会社西東社,2019